御船町役場から山都町方面へ、10キロほど車を走らせた山の中にある七滝神社。

元々、滝をご神体として祀ったのが七滝神社の始まりとされ、歴代の細川藩主も七滝見物に訪れた言われています。現在その滝を見られるのは年に一度、5月に開催される七滝祭りの時だけですが、滝に水が流れていない時でも十分見応えがあります。

はじまりは南北朝時代の観応2年(1351年)、阿蘇大宮司惟村(これむら)が七滝神社を創建し、阿蘇氏の祖神を祀りました。
以降戦乱の時代が続き江戸初期には荒廃していましたが、肥後細川氏第5代綱利が貞享3年(1686年)に再建、その際社殿の両側に細川氏の九曜の紋を刻み、拝殿に二基の灯篭を寄進し、現在に至っています。



江戸〜明治に描かれた絵画には、肥後国藩主であった細川韶邦(よしくに)が婦人をともなって七滝を訪れたと思しき場面も残っています。
七滝は高さおよそ40メートル、幅およそ30メートルで、阿蘇溶結凝灰岩(約9万年前の阿蘇カルデラの巨大噴火で噴出した火砕流堆積物が高温で堆積したことで溶結した岩石)と柱状節理(マグマや溶岩が冷えて固まる際に収縮してできる、岩体内の柱状の割れ目)が交互に見られ、その浸食差により七段になって落下することからその名が付けられました。
昭和12年(1937年)上流に水力発電用取水堰ができたために、普段はごくわずかにしか水が流れなくなりました。以降は大雨の後か、年に一度の七滝神社例大祭(5月の第二日曜日)でその姿を見ることができます。

普段、豊富な水量の滝を見られない代わりに見られるのが「甌穴(おうけつ)」です。甌穴とは、川底や川岸の岩に円形のくぼみができたもので、川の流水の働きにより作られます。
まず、川底に割れ目やくぼみなどがあると、そこに流水の岩を削るはたらき(浸食作用)が集中します。そこに流れ込む水は渦を生じることで浸食力が増し、円形の穴へと拡大していきます。さらに、その穴に上流から砂や石を含んだ水が激しく内壁に衝突することで、その砂や石が研磨具としてはたらき甌穴ができあがります。七滝の甌穴の中には直径3m以上のものもあり、特異な景観を生み出しています。

神社からはたくさんの甌穴を見ることができる
神社からは滝を見下ろすことができ、甌穴もすぐ近くから見られます。一方滝つぼへ下りてゆけば、下から滝を見ることができ、こちらも迫力があります。 滝つぼへ降りるのには10分程度。少し滑りやすくなっていますが、せっかく訪れたなら、神社と滝つぼ、両方行ってみるのがおすすめです。


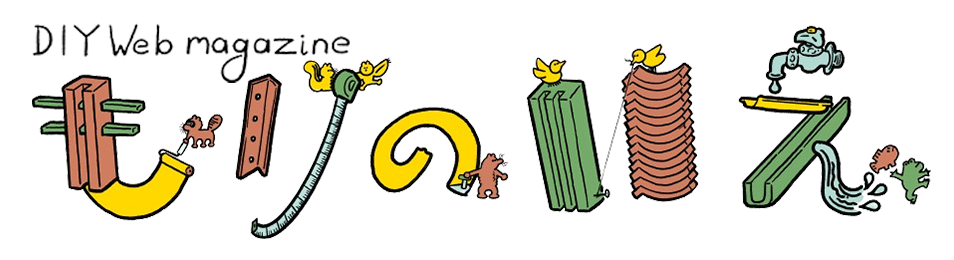
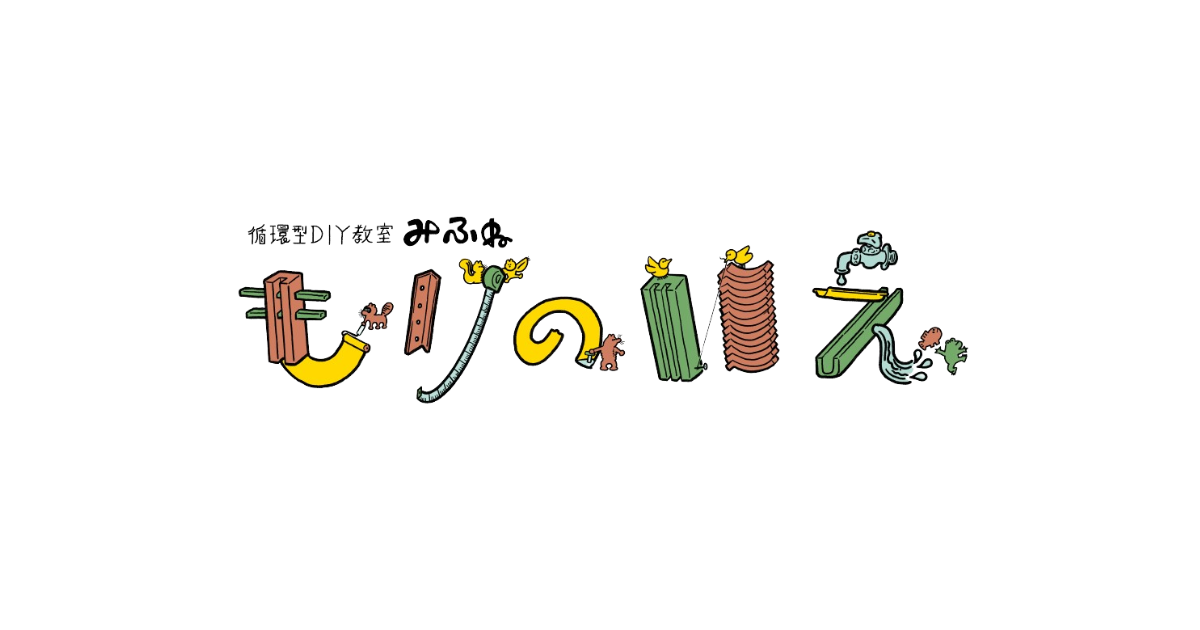
コメント