三回目は初めての平日開催。北村さんと平山さん、2名の大工さんの指導のもと、暑い暑い一日、床板張りとキッチンシンクづくりをしました。
前回は居間の足固から根太、床下地を交換して張り直しました。今回はその上に床板を張りました。
元の床の高さと揃えるために間に細い木材を入れ、その上に厚さ30mmのしっかりとした床板を張ってゆきました。
ph(下地の張られた床)
cap:根太・足固の上に張られた床下地
ph:
cap:元の床の高さと揃えるために、細い木材を入れて調整
無垢材の床板の厚みは一般的には15mm。合板のフローリングの場合は一般的な厚みは12mmで、DIY用の専用テープで施工する簡易的なものだと1.5mm〜5mmと薄い床板を使用します。それに比べるとだいぶ厚みのある床板です。これは、断熱材を入れずに冷気を防ぐためだそうです。
ph
お昼ご飯は今回、人数も多くなかったのでスタッフで準備しました。
メインは〈肥後そう川手延べ麺〉さんの素麺。〈肥後藍御船工房〉とのコラボレーション商品で、御船で無農薬で栽培されたハーブ、バタフライピーなどを使用して藍色のグラデーションを出した素麺を使って、韓国の辛いタレで食べるビビン麺を作りました。御船中山間地域の地域おこし協力隊第一号で、無農薬・無肥料の自然栽培の米農家、堀永さんのお米でおむすびも作って提供しました。
ph:(素麺)
cap:無農薬のハーブ(バタフライピー)で色付けした素麺。濃淡のグラデーションが美しい
ph:
cap:初めての大人だけでの開催。昼食時に落ち着いて交流できました
食事後、床板張りの続きが始まりました。北村さんから突然「少しでいいからご飯余ってない?」と言われ、最初は何のことかよくわからなかったのですが、これは古来から建具や家具、建築に使われていた「米のり」を作るためでした。化学接着剤が主流になっている一方で、それがシックハウス症候群の一因になっていることも指摘されています。「米のり」はお米だけで作る天然の接着剤。一説では奈良時代から日本で使われていると言われています。
炊いたお米を潰して伸ばしたその「米のり」を、床板の穴が空いているところに入れて、その上に穴の形に合うように削った木材を入れて固定。ほとんど穴がわからない状態になっていました。
Ph:(スマホから)
cap:手作業で穴に合うように木材を削る
Ph:(床穴を塞ぐ)
cap:穴に「米のり」を入れて、穴に合わせて削った木材を入れる
ph:(床板を木材で叩いて隙間を詰める)
cap:床板を木材で横から叩いて隙間をぴっちりと詰める
無垢の床板が部屋の半分張り終わり、気持ちの良い空間が見えてきました!
一方台所では午後から、前回外したステンレスの流し台の下の製作が行われていました。廃材を電動やすりで綺麗に磨いて、組み立ててゆきます。
Ph:(やすりで削る)
Cap:電動やすりで丁寧に表面を磨きます
Ph:(枠組み)
Cap:枠組みを作って
Ph:(3人でハメる)
Cap:みんなではめたらあっという間に変身!
Ph:(新しいシンク)
cap:この後引き出しも作ります
平日だったので、初めて子供がいない大人だけの作業。いつも来ていたスタッフも仕事が入っていたりで、今までよりも10人ほど全体の人数が少なく、その分ぐっと皆さんの距離が近づいたような気がする一日でした。
Ph:(集合写真)
Cap:大人のDIYデイ、終了!
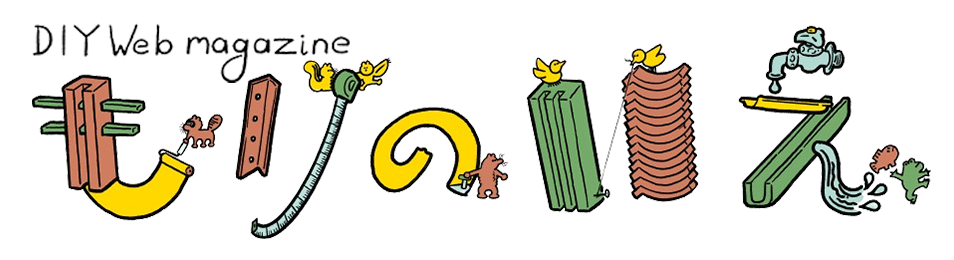
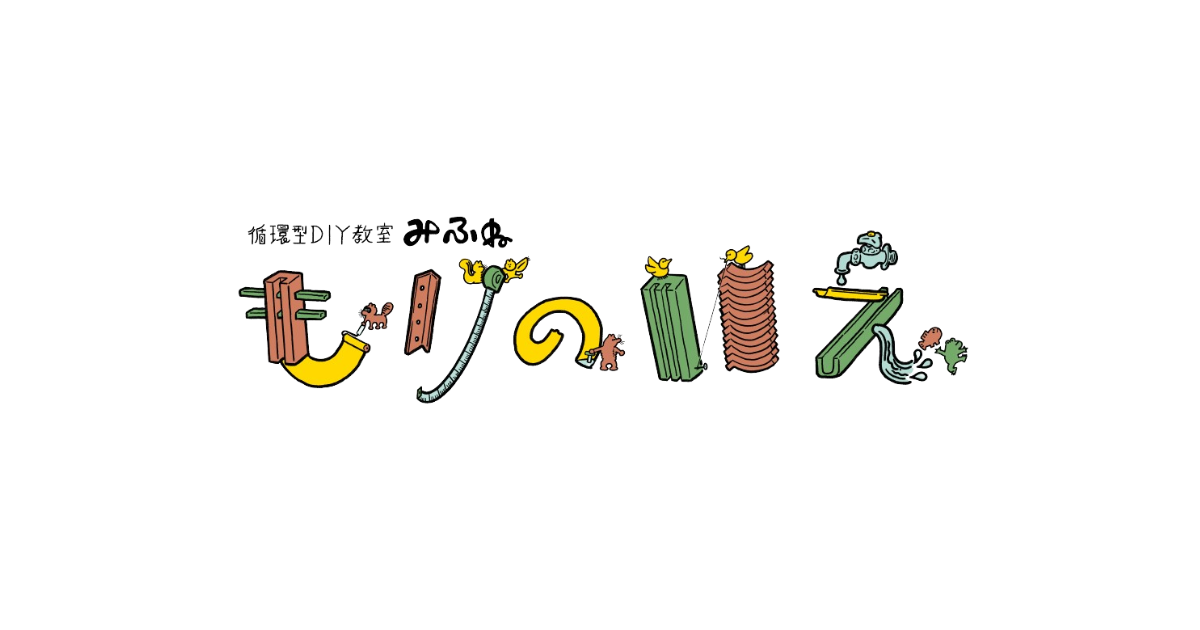

コメント